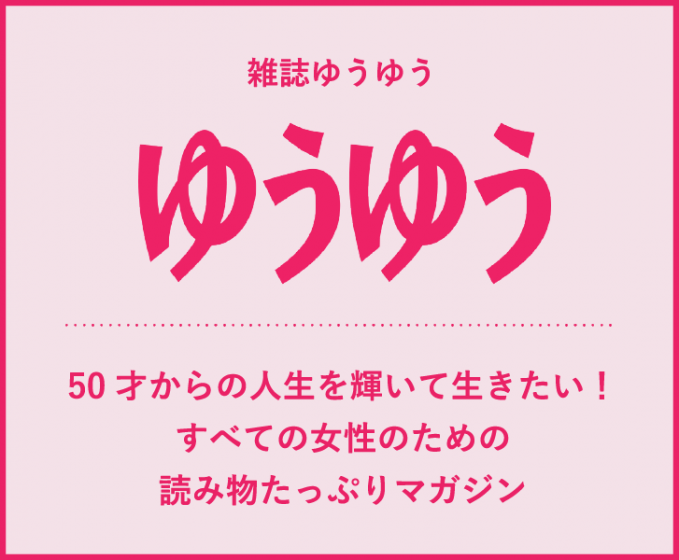【光る君へ】藤原道長(柄本佑)への変わらぬ想いを伝える紫式部(吉高由里子)。二人は唇を重ね…
公開日
更新日
志賀佳織
2024年のNHK大河ドラマ「光る君へ」。『源氏物語』の作者・紫式部のベールに包まれた生涯を、人気脚本家・大石静がどう描くのか? ここでは、ストーリー展開が楽しみな本ドラマのレビューを隔週でお届けします。今回は、第21回「旅立ち」と第22回「越前の出会い」です。
前回はこちら↓↓
【光る君へ】紫式部(吉高由里子)と藤原道長(柄本佑)の過去の恋愛模様を、紫式部の父についに告白
ドラマの開始から5カ月を迎え、いよいよ第21回、22回から物語は第二章ともいうべき新たなステージに入っていく。タイトルの「旅立ち」は、まさに、さまざまな人物たちにとっての旅立ちが描かれていて、感慨深い回である。
藤原伊周(これちか/三浦翔平)、藤原隆家(たかいえ/竜星涼)兄弟が花山院(本郷奏多)に矢を放ち、死者を2名出してしまった「長徳の変」に対し、伊周は太宰権帥(だざいのごんのそち)、隆家は出雲権守(いずものごんのかみ)として配流(はいる)されることが決まった。
なかなか勅命に従わない伊周の身柄を捉えようと、二条第に乗り込んだ検非違使(けびいし)の剣を抜いた中宮・藤原定子(さだこ/高畑充希)は、自ら衝動的に髪を下ろしてしまった。その報告を受けた一条天皇(塩野瑛久)は、いまだ処分に従わない伊周に憤り、勝手に髪を下ろしてしまった定子も同罪だとなじる。
しかし、厳しい言葉を発した直後、藤原道長(柄本佑)と二人になると、定子が自分に二度と会わない覚悟を決めたことに今さらながら衝撃を受け、そこまで追い詰めてしまったことを悔い、号泣するのだった。
定子のことが心配だった定子の女房・ききょう(清少納言/ファーストサマーウイカ)は、まひろ(後の紫式部/吉高由里子)とともに民に扮して二条第の茂みに潜み、その一部始終を見ていた。後日、屋敷を訪れた藤原宣孝(のぶたか/佐々木蔵之介)に、そのことをまひろが伝えると、身を乗り出して興味津々の宣孝は、「帝のお心をおひきつけになるぐらいの方だから、中宮様はよい女子なのだろう。もったいないな」などと調子に乗った感想を漏らして、まひろの顰蹙を買う。
この宣孝とまひろ、最初はまひろの父・藤原為時(ためとき/岸谷五朗)を介して娘と父の友人の会話であったが、回を重ねるごとに、どんどんまひろが宣孝と同等に応じられるようになっていく様が描かれていて興味深い。しかも、まひろが本来のまひろらしく、この宣孝の前では「型破り」で「破天荒」な性格を素直に出せているのが印象的だ。2人の間に決して色っぽさは感じないけれども、なにか「馬が合うぞ」と思わせるリズミカルな会話が実に楽しい。
宣孝は、「おいおい」と言いたくなるような「おやじ度」の高いところもある人物だが、その見聞の広さで宋(そう)の国の事情を教えたり、父の昔話を聞かせたりとまひろの目を開かせていく、そんな大きなところも見受けられて「ほぉ~」と思わせる。その宣孝が、今回、この定子の出家のことを聞き、こう漏らすのだ。「この騒動で得をしたのは誰であろうか。右大臣様であろう。花山院との小競り合いをことさら大事にしたのは右大臣だ。右大臣が女院と手を結び、伊周を追い落とした。これは右大臣と女院による謀かもしれぬ」
動揺を隠しつつまひろはこう静かに答えるのだった。「いえ、なるほどと思いました」
一方、伊周はなんとかして都に留まろうと逃げ続け、捕らえられそうになると、ひっくり返って泣く始末。妹である定子に「見苦しゅうございますよ、兄上」と一喝されるが、駄々をこねる。
結局、見かねた母・高階貴子(たかこ/板谷由夏)が「母もともに参るゆえ」と言ってその場を収めるのである。いやぁ、ママ、それはダメでしょう。お気持ちはわからないでもないが、いっぱしの大人ですからね、息子さん。この伊周のあまりの往生際の悪さがなんともいえず見苦しいのだが、演じる三浦翔平が実にいい味を出している。
案の定、一条天皇の逆鱗に触れ、母子は引き裂かれて、伊周は一人、太宰府に向かうのだった。さらに二条第が火事になる。中宮・定子を心配して救いに駆けつけるききょう。「私はここで死ぬ。生きていても虚しいだけだ」という定子に、ききょうは半狂乱になって訴える。「なりませぬ! おなかの御子のため、中宮様はお生きにならねばなりませぬ!」
この騒動の働きを評価された道長は、左大臣へと出世した。そして、内裏では新しい后探しが始まる。すっかり元気になった女院こと藤原詮子(あきこ/吉田羊)が、道長にいろいろ意見をしてはしゃいでいると道長の妻・源倫子(ともこ/黒木華)が笑う。「女院様があまりにお元気になられましたので」。すると詮子も明るくこう答えるのだ。「もう呪詛されておらぬゆえ」
今回ここがある意味、非常に見応えのある見逃せないシーンだと思うのだが、この倫子、ついにこんなことを言ってしまうのである。「あの呪詛は不思議なことにございましたね。女院様と殿のお父上は仮病がお得意だったとか。ふふふ」。あんぐりという感じで倫子を見つめる道長と、怒りと衝撃を抑えつつ、なんとも複雑な表情をする詮子。一瞬の睨み合いが、実に恐ろしい! これも「旅立ち」のひとつかもしれない。倫子が道長の出世とともに、堂々と力を増していくその片鱗がうかがえるのだ。明らかに女院様との立場が逆転した瞬間だった。
再び定子に仕えるようになったききょうは、ある日まひろを訪ね、定子が懐妊していることを告げる。「生きながらに死んでいる」と自らを言う定子を励ます手立てはないかと思案するききょうに、まひろは「四季のことを書いて励ましてみては」とすすめる。
のちに『枕草子』となる随筆を、ききょうは毎夜したためては、傷心の定子のもとに届ける。それを目にする定子。「春はあけぼの」「夏は夜」とその書が届くたびに、定子の心は癒やされていく。
権謀術数ひしめく貴族の世ではあるが、一方でこうした雅の文化が築かれたのもこの時代。それがきめ細やかに描かれているのが、見ていて非常に楽しい。紫式部と清少納言が実際に会ったかどうかなんてこの際どうだっていいのである。ひととき平安の昔に飛べる、そうした脚本と演出の力がこのドラマの一つの魅力でもあるのだ。
いよいよ、まひろの「旅立ち」も迫っていた。父に伴い、越前に赴くのだ。出立前に意を決すると、まひろは道長をかつてよく会った廃邸に呼び出す。そして聞いておきたいことがあると、こう切り出す。「中宮様を追い詰めたのは道長様ですか。小さな騒ぎをことさら大事にし、伊周様を追い落としたのもあなたの謀(はかりごと)なのですか」。間髪入れずに「そうだ」と答える道長。「だから何だ」
その目を見たら、道長がそんな企みをしたのではないことが一瞬にしてわかったまひろ。そしてこう告げるのだ。「この10年、あなたを諦めたことを後悔しながら生きてまいりました。いつもいつもそのことを悔やんでおりました。いつの日も、いつの日も」。道長もまひろを思い続けていたと言う。「いつの日も、いつの日も、そなたのことを」
「今度こそ越前の地で生まれ変わりたいと願っておりまする」。まるで歌うかのように交互に交わされる「いつの日も」。ここは後々まで残るであろう名場面だ。この夜のシーンから、パーッと開けて俯瞰で琵琶湖の舟が映る。まひろの人生が次に進んだことが晴れやかに伝わってきた。